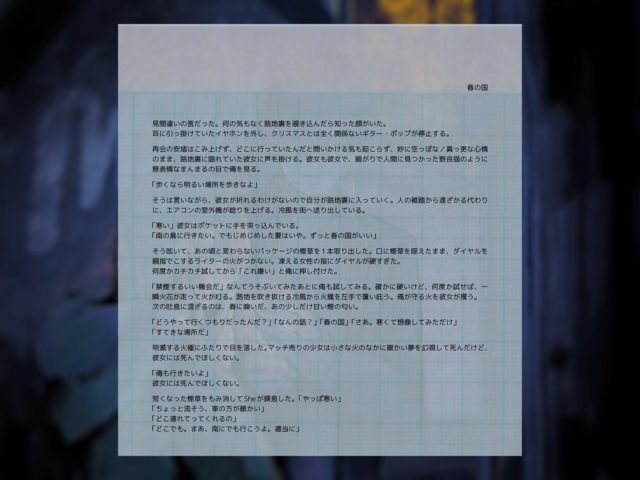メリークリスマスなのでとても久しぶりに『She Sells Sea Shells by the Seashore』を書きました。
本編とは関係ないifの話です。
春の国
見間違いの筈だった。何の気もなく路地裏を覗き込んだら知った顔がいた。
耳に引っ掛けていたイヤホンを外し、クリスマスとは全く関係ないギター・ポップが停止する。
再会の安堵はこみ上げず、どこに行っていたんだと問いかける気も起こらず、妙に空っぽな/真っ更な心情のまま、路地裏に隠れていた彼女に声を掛ける。彼女も彼女で、暗がりで人間に見つかった野良猫のように無表情なまんまるの目で俺を見る。
「歩くなら明るい場所を歩きなよ」
そうは言いながら、彼女が折れるわけがないので自分が路地裏に入っていく。人の雑踏から遠ざかる代わりに、エアコンの室外機が唸りを上げる。冷風を街へ送り出している。
「寒い」彼女はポケットに手を突っ込んでいる。
「南の島に行きたい。でもじめじめした夏はいや。ずっと春の国がいい」
そう呟いて、あの頃と変わらないパッケージの煙草を1本取り出した。口に煙草を咥えたまま、ダイヤルを親指でこするライターの火がつかない。凍える女性の指にダイヤルが硬すぎた。
何度かカチカチ試してから「これ嫌い」と俺に押し付けた。
「禁煙するいい機会だ」なんてうそぶいてみたあとに俺も試してみる。確かに硬いけど、何度か試せば、一瞬火花が走って火が灯る。路地を吹き抜ける冷風から火種を左手で覆い庇う。俺が守る火を彼女が攫う。 次の吐息に混ざるのは、春に嗅いだ、あの少しだけ甘い煙の匂い。
「どうやって行くつもりだったんだ?」
「なんの話?」
「春の国」
「さあ。寒くて想像してみただけ」
「すてきな場所だ」
明滅する火種にふたりで目を落した。マッチ売りの少女は小さな火のなかに暖かい夢を幻視して死んだけど、彼女には死んでほしくない。
「俺も行きたいよ」
彼女には死んでほしくない。
短くなった煙草をもみ消してSheが嘆息した。「やっぱ寒い」
「ちょっと流そう、車の方が暖かい」
「どこ連れてってくれるの」
「どこでも。まあ、南にでも行こうよ。適当に」
イラスト
原作『She Sells~』
『She Sells Sea Shells by the Seashore』
“これは思い出話であり、書くことに意味はないし、書いたことは音遊びで、これは物語ではない。”
順番のない紙片による掌編小説集。ページをリロードするたびに、ランダムに1つの掌編が「再生」されます。