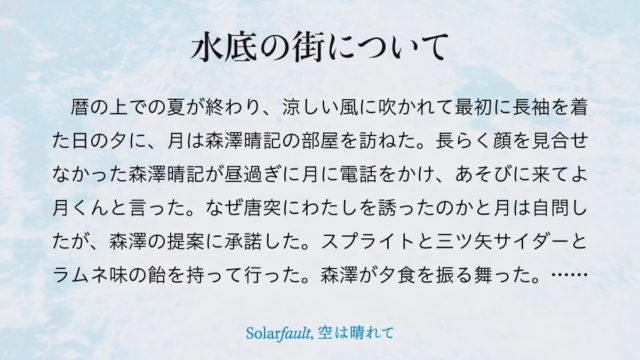fragments

筆を執った。外気はとても寒く、壁の薄いこの家で温かいミルクコーヒーを飲みながら、昨夜の通話と今日の出来事を丁寧に思い返す。夕暮れにそびえる工場のことを思い出す。今日、はじめて工場長に会って、二言三言会話を交わした。もうこんなことはやめにしたいと、工場長は言っていた。夕闇を背負った工場の巨大なシルエットがぼくにも工場長にとっても苦々しい城砦のようにしか思えなかった。
自分を主人公において書くのはとても難しい。現実対虚構の二項対立に散々惑わされつづけたぼくたちは、虚構と現実を隔てるのは劇場の舞台と客席のようなステージ一段の段差ではなく、段階を踏まないスロープであり、現実は意図せず虚構に転がり、虚構もまた意図せず現実へ流れ落ちるのだと身をもって知ることになる。自分が虚実の間のどのレベルに立ち、ものを見て理解し記すのか、未だに測りかねている。だんだん目が冴えてきたので続きをしばらく書けそうな気がする。深夜の冬はいっそう深く冷え込む。
対話は映像で行われる。端末のインカメラで互いの姿と背景を映す。通信料金は国際電話よりもはるかに安い。手紙を書くよりも安い。
「そっちは今日もあたたかそうだね」寒い部屋からぼくは呼びかける。
彼女の背景はいつも凪いだ大西洋が広がっている。時にハイビスカスと彼女が呼ぶ赤い花々が咲いている。砂は日差しを反射して白い。
「とてもいい天気」
ふたりの会話はわずかに一呼吸分のタイムラグを生じさせる。
「そっちはどう?」
彼女はいつも海辺に端末を持参して戸外でぼくに電話をかける。
「とても寒いよ。北風が冷たい」
フィリップ・K・ディックが作中に〝映話〟を用いたことを思い出した。ぼくの両親が生まれた少し後に書かれた小説で、現実にテレビ電話が発明されるよりも前に造語として映話という架空のマシンが導入された。
「信じられない。こっちは今日もいい天気」
現実には発明された機能は映話とは呼ばれずに、カメラ付きインターフォンやSkypeに始まる各社開発のアプリケーションサービスがサービス独自の名前を名付けられた。携帯通信端末の大普及は誰にも予言できなかったのではないかと、ディックを読み返したときにふと思った。
「本当にきれいなところだね」
ディックが幻視した「未来」には公衆映話が存在した。それには笑った。ひとりひとりがテレパスのように連絡手段を携行するのが当然で、肉声を重ねることよりも短文での文字伝達ばかりが優位になるこの現代を誰が予言できただろうか。
「あなたのところは夜?」
もう前時代のようによそよそしい技術に感じられるが、かつてのひとびとに留守番電話がなした功績というものを、最近ときどき考える。
「もうすぐ日付が変わるよ」
外出中、開封されない手紙。行き違い。伝言板。待ち合わせの失敗。齟齬の機会がひとつずつ丹念に潰えていく。どんな些細なメッセージにも開封を知らせるマークがつく。
「こっちはお昼過ぎ」
伝えられなかった。会えなかった。伝達失敗の機会は通信技術の発展により今後ますます減っていくだろう。人間は全知でも全能でもないが、こと情報伝達に関してはその域へ至る糸口がおぼろげながら見えそうだった。
「昼は何を食べた?」
呼びかければ誰もが応えてくれる。生きているうちに一度も孤独な瞬間に立ち会わない人間も、もしかして今この時代にいるのかもしれない。
「カキを頂いたの。ハルキは?」
孤独の機会は潰え、窄まれ、孤独それ自体について語る機会は失われ、孤独はまるで病理のように治療の対象として扱われるか、辞書にしか書かれていないまぼろしであるかのようだった。ぼくは、
「いつも通り、焼鮭とカップのみそ汁」
孤独だった。確信はあった。
「いいじゃない。こっちは醤油が恋しいよ。たまには白いご飯が食べたいな」
数日に一度は映像を介して会話を交わしているが、大洋を挟んで隔てられた距離は揺るぎようがない。
「ぼくだって美味いカキが食べたいよ」
フィジカルな願望は共有できないし、そもそもぼくたちは映像を通じて触れ合えないので、これ以上の伝達は叶わない。技術的に。あとは現地に赴くしかない。
「ふふふっ」と小さな声で彼女はわらう。明るい午後の光。「そろそろ遅いんじゃない?」
時差もまた永久に無くなることはない。こればかりは分布を広げすぎた人間の落ち度だろう。
「ごめんね、気を使わせちゃって。ありがとう。もう寝ようと思う」
ぼくの言葉が届くまでの間、彼女の映像はいつもひと呼吸だけ動きを止める。言葉が耳から大脳に波及するまで待ってくれているようである。
「じゃあわたしもベランダで昼寝しようかな」
実際タイムラグの原因はぼくの端末が古いだけだが。
「こっちは実は日付が変わったんだよ」
でもぼくのせいではない。
「そっちはもう明日なんだね」
午後の太陽が今は彼女の国を照射している。
「昨日だよ」
ぼくは今日の日没を思い出している。
「おやすみなさい。今日もおつかれさま」
大西洋を臨む彼女はそこで美しい日没を見るのだろう。
「おやすみ」
接続を切った。かたわらに置いていたコーヒーはもうぬるくなっていた。
眠りに就くまでの間、眠る姿勢が定まらず、シーツの中で何度も寝返りを打ち、自分に見合った身体を獲得しようとする。眠りへの強い希求は訪れないが再び目を開ける気にもなれず、目を開けたところで消灯した部屋の窓のカーテンの隙間から夜の赤みを帯びた薄暗い外光がぼんやりと壁に差す程度だった。その黄色のような茶色のような赤褐色の光のもやは、家々の蛍光灯や街灯の白色灯に尾灯やフォグランプや航空障害灯の明滅や信号機の赤色灯が混ざり合っているのだと思う。夜の地平は赤い。朱い。赤い夜の明滅が、眠っている人の静かな呼吸に、呼吸を導く心臓の拍動に結びついて、思考認識のなかの同じ引き出しに収められた。眠りに就こうとするぼくが想像する眠っている人は自分自身でもある。「眠っている人の集合」は「自分自身」を含む。眠りに就こうとするとき、意識が横たわる身体を手放しかけたその直前、意識は想像上の風景のなかを滑るように飛び回っている。鳥の飛行というよりも車や列車の走行のような速度となめらかさで、見覚えのあいまいな風景のなかを延々と走っていく。上手く走り続けられると快くなる。静かに眠りに就く身体を離れ、意識は飛び回る。どこへ? 外の世界へ、速度を求めながら、急カーブで脱落する自意識たち、を、まだ自認できる。風景はいつも戸外で、アウトバーンのように高速で、あらゆる事象は背後に流れる。思い出すに、意識は、身体を離れ、果てのない遠くへ行こうと願っているのだ。実在という枷を抜け出て自由を希求する自意識たち。目的地をこの自意識は知っている。安易なモチーフ。安直な夢。しかし身体は眠りの床のなかでどっしりと重力に身を横たえ瞼を開けようともしない。プールに沈んだ電極付き脳みその見てる夢よりも憐れかもしれない。言葉と思考を司る自意識が振り落とされた瞬間がぼくにとっての眠りのはじまりではないかと思う。そこから先のことは知れない……