
2014年から販売していたスイマーズの書籍『VANITAS』が2022年に完売しました。これまで多くの方にお手にとって頂きありがとうございました。
本作『VANITAS』は再版を行わず、書籍のPDFデータを無料で配信します。
掲載作のうち、山川夜高作『入江にて』の本文テキストを公開します(13600字)
入江にて
兄が帰ってきた日は特別おだやかで凪いでいた。晴れた日、妹が庭で洗濯物を干していると、白い軽トラックに乗った兄が知らせもなく帰ってきた。車を停めて降りた兄が、葬儀で着るような礼服の黒いスーツを着込んでいたので驚いた。かつての葬儀のときは兄もまだ学生だったから、スーツではなく黒い学生服を来て、お堂に正座したのを思い出した。
トラックの荷台から魚の入ったクーラーボックスと野菜と生活用品を下ろしたが、まだ一つブルーシートにくるまれた大きな荷物が残っていた。長さ二メートル程の細長い丸太のような大きさで、妹が生魚を冷蔵庫に仕舞いに行っている間に、ブルーシートは解かれていた。台所から戻ってくると、車の脇に立つ兄の隣に男がひとり立っていた。ずぶ濡れで表情のない知らない人物だった。
けさ海で拾ったと兄は言った。水面に浮かんでいるその男を兄の乗っていた漁船が拾い上げ、発見者である兄が引き取って連れてきた。見つけたときにはもう事切れていた。おれが見つけたからしょうがなかった、日頃言葉少なな兄がぽつりと付け足したのを妹は聞いた。
海面に浮かんでいたという水死体は、自分の力で立って歩いた。色あせたような白いシャツに蒼白い肌をして、頭のてっぺんからつま先までぐっしょりと水に濡れている。でも死んでいると兄は言った。動きはすれど、何もしない。時間が経てば溶けてしまうらしい。それまで家に置いておくと言った。しばらくこの家で飼っておくと。
家には上げられないと妹は反じた。だって死んでいるのだ。それに濡れている。兄は、それなら縁側か風呂場に置こうと提案した。妹は風呂場にも上げたくなかったが、かと言って外に置いておいても仕方がない。だから縁側に座らせて、日中庭に出しておくならいいと折り合った。作業は水死体を庭から縁側へ連れていくところから始まった。兄も妹も水死体に触れようとはしなかった。水死体は思いのほか従順で、かんまんな動きではあるが、呼べば兄妹についてきた。はだしでいる水死体を家にそのまま上げるのはためらわれたので、兄は死体の足を拭く雑巾を取りに家の中へ入っていき、妹と水死体が残された。
妹は小柄な方で、水死体は背が高い。顔を盗み見ると、生前からなのか死んだせいなのか分からないが、目鼻立ちはとても薄く印象のない容貌だった。表情は全くない。何をしていても無表情だった。
不意に目を伏せた死者と目が合い、妹はどきっとして目を逸らした。一瞬見えた死者の目は真っ暗で、深く底の知れない濁ってよどんだ色をしていた。
死者はあらゆる風景を一応眺めていたらしい。あたりを眺め、聞こえていたが、物を考えてはいなかった。ぼうっとあたりを見ている死者を誘導して雑巾を踏ませた。けれども足を拭いたところで、廊下を歩けば死者はまた足元を水でびしょびしょにした。待つようにと命じると死者はそこで足を止めた。命令は通じるようだった。
昼時、妹が野菜炒めを作り、廊下に面した和室に座って兄妹は昼食を取った。兄はたまにしか帰ってこないが、面と向かって会えるときでも、兄妹はあまり会話を交わさない。水死体は縁側にいて、家の庭やその向こうに見える海を眺めているようだった。三月の午後はおだやかで何ひとつ起こらない。開け広げた戸の向こうから潮風がかすかに吹き込んでくる。
じきに兄は畳に寝転がって午睡した。妹は食器の片付けがてら、邪魔にならないように部屋を出ようとして、しかし縁側に水死体を残しているのを思い出した。死者を一人にしてはいけないのかもしれない。人を襲いは、まさか、しないだろうけど、それでなくても行動が読めない。死んでいる彼は妹に背を向けて、生きた人間には興味がないというように、ただひたすらに海を眺めているようだった。兄の寝息が聞こえてきた。食器の片付けと麦茶を取りに台所へ向かった。その家は一本の長い廊下で玄関から奥の間までつながっていて、庭に面した廊下を縁側にしている。
使っていないガラスのコップを戸棚から引っ張りだして麦茶を注いだ。妹自身の分と合わせて二杯の麦茶を廊下に持っていった。廊下に戻ると板張りの床には水死体から浸み出した水がじっとり広がっていた。あとで雑巾がけをしようと考えながら、雑巾がけをするために彼を上手くどかせるだろうかと心配はあったけれど、妹は彼に麦茶のグラスを差し出して様子を見た。彼ははじめ麦茶にも妹にも気付いていないようだった。
あの、と妹は呼びかける。「お茶いりませんか」
死者は答えなかった。返事はないが、かんまんに妹のことをふり返り見た。妹は目を逸らした。まだ死者を正視できないでいた。
まるでお供え物みたいに差し出された麦茶に死者は手をつけなかった。死者におそれを抱いてはいたが、妹は辛抱して彼の傍にいてみることを努めた。長い午後の時間に妹は退屈していたし、おそれはしていたが興味はあった。
「あなたの名前は」と妹は訊いた。返答はもちろんない。死者は海を眺めている。洗濯物が日差しを浴びてやわらかそうに見える。
庭はひらけていて海を臨めるが、砂利ばかりできれいな花もない。勝手口や納戸の脇に小さなサボテンを飾っている。防砂林には満たないが、庭の向こうには緑が茂り、けもの道を下っていくと砂浜まで歩いて行ける。海岸にはときおり何かが打ち上げられている。家から西の方にまっすぐ行くと、波止場が伸びているのが見える。あちら側が漁業の中心地であり、この家は町はずれに建っている。
兄は着ていたスーツを脱いで、シャツに短パンと、楽な格好で眠っていた。三月の日中とはいえ風が吹き込めば涼しすぎる。妹は兄にタオルケットを持ってきた。日焼けした兄の姿は帰宅する度にやつれを重ねているように見えた。妹は兄の話が聞きたかった。仕事のことや死者を拾ったいきさつについて。でも兄も死者も家の中で黙りこんでいる。妹は洗濯物を取り込んだ。兄の衣類をたたんで仕舞った。
夜分、夕食を取っているとき、兄はまた明日から仕事に出て行くと告げた。兄妹が食卓にいる間、死者は雨戸の内側に立たせていた。廊下が死者の定位置になりそうだった。あれを家に置いておくと兄は言った。いつまでもつか分からないけど家で飼っておく、と。次はいつ帰るのかと妹は訊いたが、兄は分からないと一言答えた。遠くなりそうだと妹は思った。死体は兄が帰るまで傷まずにもつのか。あれは喋ったりするのだろうか。兄は魚のあらを細かく刻んで死者に与えた。死者は若干の興味を示したが、口元まで魚を持っていっても食べることはしなかった。食べ物は要らないらしい。びしょ濡れになった床を見て、こいつはときどき動かさないと駄目だなと兄が呟いた。向かい合う兄と水死体は同じぐらいの年齢に見えた。漁師の兄は日に焼けて、水死体は蒼白だった。妹は死者にあれこれ試す兄の様子を眺めていた。
翌朝兄妹は早起きして、兄が身支度する間に妹は兄の弁当を作った。車に乗る兄を見送りに出ると、兄は妹の頭に手をおいて、しかし別れの一言も言わなかった。彼らはお喋りを交わして絆を築いた兄妹ではなかった。少なくとも兄はそういうことをしなかったし、妹もそれに習った。
妹は洗濯物を回した。死者は一晩中廊下にたたずんでいて、眠りをとった様子はなかった。「おはよう」と妹は声をかけた。洗濯物を出すのに邪魔なので、妹は死者を一歩どかせた。縁側のガラス戸を開けていると、死者はいつの間にか背後について来ていた。あたりをうろつき回りはせず、洗濯物を見ていたり、じっとその場にうつむいていたり、向こうの海を眺めていた。洗濯日和で風もなくおだやかな陽気だった。いつでもそうだったと妹は知っていた。妹は彼のための雑巾を洗って干した。少なくとも兄が帰ってくるまでこの家で飼うつもりなのだから。
水死体と一昼夜を過ごし、彼が無害そうであると、妹は判断した。過度に接すること、触れること、同じ食器やタオルを使うことは避けたいが、妹と死者の隔たりはその程度なのかもしれなかった。死者は常にずぶ濡れだが、汚れそうな様子はないので着替えの必要もなさそうだった。
妹は死者を連れて家の周りを歩きまわった。手持ち無沙汰だったのだ。これがサボテン、これが鉢植えと、そこにあるものを指さして子供に教えるみたいに語った。死者は頷きもしなかったが、おとなしく言葉を聞いた。戻るよと妹が言えば家の中について来た。縁側に彼を留まらせて、風呂桶に水を張って彼の足元に持っていった。足を水に浸からせてから、海水の方がよかったのではないかと思い直したが、彼が滴らせているものが海水なのか真水なのかも知らないし、彼は彼で別段変化も思うところもなさそうだった。
時間ばかりがありあまる日々だった。妹は時間をつぶすために家の掃除を日課にしていた。たんすの上を雑巾で拭き、畳を掃いて、植物に水をやる。生きているもの、生き物ではないものの世話をするのは慣れていた。ならば死んでいるものの世話も果たせるのだろうか。
妹は死者のことを何も知らない。死者はどうやら、生者をおびやかさない。答えがなくても妹は死者に近づくことにした。時間だけならあまるほどあった。妹は死者の隣に座り、海を見つめる彼を眺めた。はだしの爪がいやに白いのが印象に残った。死んでいるのだ。半開きの口が力ない。
生きていたら根ほり葉ほり尋ねていたのだろうと思った。彼は死んでいて答えない。彼の時間はもう止まっている。彼の人生は終わっている。
「でも、名前は聞いてみたいな」
なあというか、ですと言うべきか、迷った末に妹の言葉は脱力した独り言のような語尾になった。答えない人に話しかけるのは独り言も同然だし、留守にしがちの兄をもったためか独り言は多い方だった。それに、ここには妹と彼しかいない。年長者である彼に対して、やはりですますの方がよかっただろうか。
妹は兄の荷物のなかから彼の遺品を探そうとした。それらしいかばんの一つも見つからなかった。身の回りの物は揚がらなかったか、はじめから持っていなかったのかもしれない。しかし自分が身元を知ったとして、どうするというのだろうか。彼の生まれや名前を知ったところで、ここにいる彼は死んでいる。どうもしてやれないのだと妹は悟った。
溺れたのだろうか。船が沈んだんだろうか。彼は自殺者のような気がした。身投げしてここに流れ着いたのだと想像するのが一番似合った。
縁側に戻ると彼は変わらない姿勢で座っていた。動くなと言いつければ一日中微動だにしなそうだ。でも全く動かないでいて、蝿がたかったら困ると考えた。うじが湧いたら飼うことはできない。そのときはまた海に沈めたほうがいいだろうか。
海は凪いでいる。彼にも過去があるということを妹は知っている。
「水死さん」、失礼か。
「名無しのごんべえ」、全然似合わない。
名前のことは切り上げて妹は食事にした。妹がいない間、死者は廊下のどこかに座り込んでいるらしい。入っていい部屋、いけない部屋は既に教えこんでいた。畳の部屋は入ってはいけない。台所と玄関も入らない。風呂場、手洗い場もあまり入れない。結局、廊下の奥のほうになる。だいたい縁側のあたりである。じきにタオルかマットを敷こうと妹は考えた。
長い間、ほとんどの日々を妹は一人で過ごしてきた。廊下に彼という視線があるのは、ときどき妹を不慣れな気分にさせた。彼は見ている。雨戸を閉ざすと海が見えないので、家の中の物を見て過ごしている。彼は見ているだけで、きっと考えてはいない。真っ暗になった家の中でも、目も瞑らずにたたずんでいる。暗闇の中から蒼白い姿がかすかに浮かぶことがある。妹が彼に対して何か気にするようなことはないのだ。
消灯する前に声をかけた。
「おやすみなさい」
返事はないし、水死体はきっと眠らない。
布団に入って彼の名前をあてどなく考えていると寝付けなくなった。彼のための縁側の足拭きのことを連想して、彼が風呂にはいる必要性、虫がつかないように清潔に保たなければならないと考えた。でも彼は死んでいる。そのために自分が彼の身体を洗わなければならないと思い、妹はひどく不安になった。死者のずぶ濡れの白い素肌を触れようという気にはなれなかった。そういう点において、たとえ彼が人のように自立して過ごしているとしても、生活と死者の決定的な隔たりを悟った。妹は死者をおそれていた。たとえこれから飼うと決めたとしても。
翌朝、ヨドミという素敵な名前を思いついた。失礼な聞こえ方はしないし、よどんだ目という由来もあって、妹は呼び名をなかなか気に入った。早速廊下にいた彼に「おはよう、ヨドミさん」と声をかけた。名前を与えられても死者はやはり何とも思わないようだった。
「雨戸を開けるよ。洗濯物が終わったら散歩に行かない? ちょっと待っててね、サンダルを探してあげる。はだしのまま出歩いたらガラスを踏んで怪我するかもしれない」
矢継ぎ早に声をかけたら意味を聞き取れないだろうか。そう分かっていても妹はまくし立てた。
「まだここにいて待っていてね。わたしはご飯を食べて着替えて髪を結んで、洗濯物を回して外に出さなきゃ」
ヨドミ氏は相槌も打たなかった。妹はとても満足した。朝の仕事を片付けて、使われていないサンダルを下駄箱から引っ張りだした。外は晴れ、おだやかなそよ風が海の方から吹いてくる。
生垣の間のけもの道を下って海の方へ出た。家は丘の上にあって、少し下ればすぐに砂浜にたどり着く。浜は小さな入江である。魚が打ち上げられていて、二羽のカラスが目玉を突いていた。
さざ波が浅瀬の砂をかき混ぜて、巻き上げながら砂浜に押し寄せた。波打際の水は砂が混じって濁っている。沖に出ればけっこうきれいだと兄は言っていた。波打際が濁っていても、晴れた日には海は青く、沖では海底が見えることもあった。ヨドミ氏は今までで一番強い反応を示し、海をじっと凝視していた。
家に一人でいても仕方のないとき、妹は浜に足を運んだ。波の寄せたり引いたりするのを見ているのは好きだった。ときどき魚影を目撃できた。浜に流れ着いたものを探して歩くのも楽しみだった。
ヨドミ氏は茫然と遠くの方を眺めていた。水平線はもやがかかって白んでいた。何を見ているのか知りたくて、妹は死者が見ているさまを見ていた。海は凪いでいた。死んだ魚のほかには変わったものは上がっていなかった。魚の死体に近づくと、カラスが鳴いて、ほんの少し遠くに飛び立ち、また着地してこちらを伺った。カラスにヨドミ氏が突つかれるのを妹は避けようと決めた。飼うにあたって、食い荒らされて傷がつくのは絶対に避けたかった。カラスはヨドミ氏を気にしているだろうか。ずっと同じ場所に立ち尽くしていたら、動かないエサだと思われて襲われるかもしれない。妹はヨドミ氏を歩かせた。それから、いつも上空を飛んでいるトンビにも気をつけなければならないと思った。
海外線に沿って歩いた。目を離すとヨドミ氏はふらふらと遠くに行ってしまいそうである。見失わないこと、動物から遠ざけることを守らなければならないと、これからの生活のことを考えた。
ずっと昔、妹は覚えていないのだが、兄が犬を飼っていた。仔山羊ぐらいの大きさの、茶色く鼻の長い犬だった。その犬が死んで、今度は猫が家に寄りついた。その猫もいつしか現れなくなり、今では動物は家の隅に巣を張っている蜘蛛ぐらいしかいなかった。
昨日のうちは、はなから、水死体はすぐ死ぬものだと考えていた。死体が犬や猫ほどに長く生きるとは思えない。でも名前をつけて散歩させてみると、少なくとも縁日の金魚よりは長持ちしそうだと思いはじめた。妹にとって背の高いヨドミ氏を連れて歩くのは気分がよかった。鳥に気をつけながらあたりを歩いて、家に戻ったのは昼過ぎだった。
食料品を買いに行こうとして、留守中のヨドミ氏の対処に悩んだ。出掛けるたびに雨戸を引いて閉じ込めるなんて大げさである。動かないようにと言いつければきっとそれを守るので、一時的に風呂場に閉じ込めた。外鍵はかけられないが仕方がない。なるべく急いで、しかも今後死者を置いて出歩く必要の少ないように、いつもより多く買い込んだ。帰宅するとヨドミ氏は風呂場の床に座り込み、浴槽に残っていた水を海を見ていたときのように凝視して待っていた。縁側に連れて行って庭から海を見せ、おとなしくしている間に風呂場の掃除をした。ずぶ濡れの死者が滲ませる何だか知れない液体が排水口に流れていった。風呂の掃除は苦ではなかった。もしも風呂に入れておいたら水槽で飼っているみたいだと思った。
縁側に座っているヨドミ氏に、ゼリーやヨーグルトや寒天やアイスクリームを少量ずつすくって取り分けて、彼が食すかどうかを試した。スプーンは使い捨てのプラスチック製のを買ってきた。死者に自分達の使う食器を使わせることは出来ない。ときおりこうやって、潔癖感により、妹はヨドミ氏の死を決定的に自覚する。ヨドミ氏はヨーグルトには見向きもせず、バニラアイスも興味なく、ゼリーと寒天は口をわずかに開けたが飲み込まず、口から破片がこぼれて落ちた。半開きの口の中は肌の色よりも血色が悪く、湿って蒼白な舌が伺えた。妹はかつて葬儀で見た白ユリの肉厚な花びらを思い出した。なめらかでいて血が通っていない点で、生花は遺体を連想させた。その口の中に宛てがわれたスプーンは、死者の内部に深入りしたために、もう生きている者が使うことはできない。生々しく、しかし死んでいる彼の唇が、寒天の破片を拒絶して吐き出すのを、妹は目を背けられずにまざまざと目撃した。しっとりと濡れた温度のない唇、それは妹に牙を剥くことは決してないのに、決定的な畏怖の対象として目に強く焼きついた。
死者の腿の上に落ちた寒天をスプーンですくって流しに捨てた。彼の素肌にも衣服にも触れたことはないが、不用意に触らないほうがいいと判断した。水浸しで真っ白いからには、生きた人間よりずっと寒天みたいに脆そうで、触れたら傷んでしまう気がした。
一方でヨドミ氏自身は何かに触れようとして手を伸ばすことをしなかった。ヨドミ氏は縁側に黙って座っていて、ときどき庭や海の方へ歩いた。歩いては立ち止まりその場にたたずんだ。花を摘んだり石を拾ったり、そういう動きをしたことはなかった。ただあたりを眺めていた。それも首や視線をきょろきょろ動かしたりはせず、海や水たまりや足元を何も言わずに見つめていた。彼の興味は極端に狭かった。食べ物を差し出してもたいがい気付きもしないように見えた。
散歩の代わりに家の中を案内した。座敷の部屋には立ち入らせない。ふすまを開いて中を見せるだけに留めた。彼も彼で家の中にいて退屈しているのではないかと思った。
彼の足音はとても小さい。ひたひたと廊下を歩くと水のはねる音がした。こまめに拭かなければ水浸しになり板が腐ってしまうだろう。彼が面白く感じるとは思えないが、家の中を歩きまわり、納屋の方もぐるりと見せた。そしてまた庭を一周して、海岸に足を運んだ。日が傾いて潮が満ち始め、南向きの海に夕日が反射してちらちらと眩しかった。目を細めた妹に対して、彼は少しも眩しがる様子もなく、ただ遠くの海を見つめていた。結局どんなものよりも海が一番の関心事らしい。「きれいだね」と妹は話しかけた。死者は会話に答えなかった。
生前の彼も海が好きだったのだろうと妹は察した。それでなくてもこの沖合で彼が死んだのは間違いなかった。死者は自分の沈んだ場所をじっと見つめているのかもしれなかった。
ふいに、ヨドミ氏がまた沈んでしまう気がしてならなくなった。「戻ろう」と妹はせがんだ。ヨドミ氏はかんまんな動作で目を伏せ、妹をちらりと見るようにしてのろのろと家へ帰った。放っておいたらヨドミ氏はまたあの海へ還るのだろうと、そう思えてならなかった。
夜、廊下の拭き掃除をして、足ふきマットの上に彼を留まらせる実験をした。板張りの床に直に立つよりもずっと良いだろうと考えた。かつて庭の片隅にあった犬小屋の様子を思い出していた。あの犬は、犬も猫も、家の外で飼っていたが、室内で飼われる犬猫が用を足すためのマットを連想した。彼は妹が命じたことを聞き入れてじっとしている。意味が伝わっていなくても生活はできるのだろう。
「ヨドミさんはどこからきたの?」
食べないだろうと思いながらも夕食の残りを少しすくって彼の口元に宛てがった。夕飯はほとんど魚だった。海辺の町では魚介に困らない。
「海は好き?」
「魚は見えた?」
「ここの海はきれい?」
「うちはどう?」
ぶしつけな言葉だと妹は自覚して、なおも語りかけていた。ヨドミ氏は傷つかない。
「本当は何か食べたかったり、やりたいことあるんじゃないかな。ごめんね、わたしが見つけられなくて。お水はいらない? 水は飲んでもいいんじゃないかな」
コップを口の端にあてて傾けたが、水は唇を伝って肌の上を流れ、死者の喉を通らない。あまりかまわない方がいいのだろうと分かっていても世話を焼いてしまう。
垂れた水の落ちる先を追って、妹は目を伏せ、「ごめんね」と零した。死んだ人には不満も希望もないのに、自分が関わっていいのだろうか、そうでなくても目の前の死者は妹にとっては年長者だった。享年三〇にも満たないだろうが、年長者であり、早すぎる死だった。
顔を上げるとヨドミ氏が妹を見つめていた。食器や花壇を眺めていたときのように、黒々とした目で穴が空くほど見ている。じっと目を合わせていると、見られているうちに自分の身体に穴が空けられていきそうな気がしはじめ、自らの無防備さにおそれを抱き、妹はまたも目を反らした。彼の口元から首元にかけてを凝視はせず視野に捉えていた。白いシャツが濡れて肌に吸い付き、色のない唇のせいで寒そうに見えた。黙っていたがひしひしと視線を感じていた。あとになって妹は、彼が自分を観察していたのだと察した。
晴れた日には洗濯物を干した。雨が降らなければ毎日ヨドミ氏と海へ出向いた。彼は茫然と何かを見つめたり興味のある方へ歩いていくだけで、相変わらずの過ごし方をしていた。妹は砂浜に目を凝らし、気に入った貝殻やガラス片を拾い集めるのを楽しみにしていた。そう毎日良い物が見つかることはなかったが、物を拾うことはずっと継続しており、家の引き出しにはかなりの数の拾い物がたまっている。
打ち上げられていた魚はいつの間にかいなくなっていた。食われて骨が残っているわけでもなく、本当にいなくなっていた。また波に流されたらしかった。あるいは誰かが拾っていったのか。
「むかしタコが打ち上げられていたことがあったんだよ」
妹は隣のヨドミ氏に語った。
「まだ生きていたけどそこら中を這ったあとでもう弱ってた。兄が捕まえて家でさばいたところを見たよ。タコの血って青っぽくて、身体を切られてもずっと動いているんだね」
腕一本になってもゆれるようにぐねぐねと動いていたのを妹は見た。魚も、さばかれてもなお生きていたときのように痙攣しているのを知っている。
タコとか、大きなものが流れ着いてきた日は嬉しい。
その日見つけたガラス片は好みの緑色をしていて気に入ったが、まだ角が取れずに尖っていたから、拾わずにそのまま砂浜に残した。ふと海中に目を向けたら、魚の群れが浅瀬に向かってぐるりと回ってくるところだった。
「見て!」と妹は声をかけた。
小魚たちは入江をひるがえってまた外洋に帰った。
ヨドミ氏も魚の群れを見ていた。まばたき一つしないようだった。そういえば目を瞑ったことがあっただろうかと妹は考えた。
見て、と言った自身の声が、叫んだときのように大声になってしまったのが、妹にはひどく気がかりになった。気にすることではないし悔やんでいるわけでもないのだが、ただ自分自身に対する気がかりだけがあとに残った。もちろん誰も、ヨドミ氏にも、妹の声は聞こえていなかった。
繰り返す潮の満ち引きで、砂浜には泡や漂着物が打ち上げられ、波の寄せた跡が幾重かの薄い線になって残されていた。濡れた砂の上の方が足場が固められていて歩きやすい。じきに妹は靴を脱ぎ、はだしになって波打際を歩いた。ふいに大波が寄せて妹の足にかぶり、まだ冷たい水温に妹は甲高い声を上げた。ヨドミ氏の足も水に触れていた。冷たい水に動じた様子はなく、日夜眺めていた海にやっと足をつけたことへの感慨にふける気配もない。変わった様子がないのを見て妹は一安心した。そして自分が死者と同じ水に浸かっていることに気付いた。あれほど気にかけていた不浄な気はまったく感じなかった。死者は妹に出会う前からこの海の中でとっくに死んでいたし、彼を除いても幾人も、それは人に限らずあらゆるものが、この海に沈んでいるからだろうと、妹は思いを馳せた。
小枝が落ちていた。波に磨かれてすべすべとしていた。妹は小枝を拾い上げ、浜に何かいたずら書きをしようと試みたが、特別書きたいことなどなかったので、棒倒しをするように砂に枝を突き刺した。
「海の中はきれいだった?」
ヨドミ氏は波に浸かるか浸からないかの狭間に立って海を見ていた。口の端からわずかに水が滴っているのが見えた。彼の足元でその液体は海水と混ざり合った。妹は彼に歩み寄った。水平線の彼方まで限りなく湛えられた水の中では、清浄も不浄もないまぜになり、等しく波に洗われた。遠くに船が静止している。
「沈んだとき、どう思った? 怖かった? 忘れ物はあった? きっと、あったよね。でなきゃ、戻ってこないよね」
今や妹の足はすっかりくるぶしまで水に浸かっていた。春の海は天候の暖かさに対してまだ冬の冷たさを残していたが、波の感触は柔らかく丸い。
「独り言なの。返事は、ないけど。本当は言いたいことたくさんあるけど、全部は言えないし、聞いてくれる人もいないし。でも聞いてほしいのかな。自分に言い聞かせて確かめたいのかな。分からない。わたしは変だね」
大きな波が寄せて、死者の足を水で浸した。返す波が砂をさらい、浜に刺した棒を倒した。黙りこんでいてもさざ波の音が絶えずあたりを満たしていた。
「わたし遠くにいてもいつも波の音が聞こえている気がする」
死者は一切沈黙していた。
「苦しかった?」
冷たさに慣れた足で、ざぶざぶと波を立てて、妹は死者に近寄った。いよいよ触れそうだとも思ったが、沈黙する死者の前に、妹は伸ばした手を止めた。死者の傍をすれ違い、はだしのまま砂浜に上がった。足元の小石を拾い上げ、凪いだ頃合いを見計らい、兄が得意だった水切りの真似をして投石した。石は一度も跳ねずに沈んだ。沈んだ石を死者は見ていた。続けて二度の投石も失敗した。じきにヨドミ氏にぶつけたくなった。無防備な背中に思い切り石をぶつけてみたいと思った。石を握りしめたまま、振りかぶっていよいよ投げつけようと思った瞬間さえあった。けれども結局妹は石をぶつけることをしなかった。それを誰かに褒められたかった。
浜に透明な塊が落ちていた。両てのひらで抱えられる位のゲル状の丸い塊である。白いコイル状の糸くずのような器官や紅色の点々が透けて見えた。クラゲは、ときどき、集団で浜に流れ着く。乾いて縮んで溶けかけたものや、もはや破片と化したものもあった。目の前に落ちていたそれはまだ生きていたときの形を残していた。
妹はつま先でクラゲを小突いた。透明でやわらかいばかりで、死んでいるのかも定かではなかった。ぶつ切りにされてなお動いていたタコと生死の見分けのつかないクラゲは、どちらの方が生きていると言えるのか、いつ死んだことになるのか、妹はしばらく思いを巡らせた。もちろん今は判断はつかないと妹は知っていた。妹は浜にしゃがみこんで、ぺったりと打ち上げられている、クラゲだった塊を眺めた。たとえば打ち上げられてしまったこのクラゲをつまんで海に投げ返したとしても、息を吹き返して再び泳ぎだすことはないだろうと直感した。
隣にヨドミ氏がいた。しゃがみ込みはしなかったが、死んだクラゲを見下ろしていた。彼の雫が妹の肩に落ちたが、妹は気に留めないふりをした。というよりもいっそその一滴によって踏ん切りが付いたとでもいうふうに、反動をつけてぐっと立ち上がり、海面をぎらぎら反射される陽の光をまっすぐ見つめた。妹は空腹を感じた。波音を除いて目に見えるものすべてが黙りこんでいた。
海岸を歩き出した。進むのはいつも漁村と反対の東の方角へだった。
疲れきってしまいたいと妹は願った。身体にむち打つつもりでとぼとぼ歩いた。そうやって時間を浪費していれば、じきに兄は帰ってくるのだ。
道程を歩きながら、妹は、思いつくままにヨドミ氏に語りかけた。見えたものや思ったことを無遠慮に投げかけつづけた。死者が応えることはないと妹はとっくに承知していた。
「でも知っているんだよ」と、その沈黙に対して妹は応じた。「あなたはわたしのこと聞こえてる」
それが自力で手に入れた、最初のお守りの言葉だった。
東へ行くと岩場を利用した小さな堤防が海へと伸びている。船着場として使われてはいない。コンクリートの上にはフジツボばかりへばりついている。妹は堤防の先端に立った。海中を覗きこむと白い影がよぎるのが見えた。死者は堤防の半ばあたりで立ち止まっていた。
入江の方へ波が寄せる。寄せる水の流れを横目に見る。自分が静止し、海面は絶えず流れているので、まるで自分の方が動いているような、流されているような錯覚に陥る。船の甲板に立って流れていく風景を見送っているような気がし始める。不在感に似た酔いだった。自分がここに立っているという事実と、自分が海上で流されているような感覚、実体験と思考がかみ合わずに遠ざかっていくさまを、妹は自覚した。酔いの自覚に妹はかすかな快楽を味わった。いまここにいるということから自由になったような気がした。同時に、実際の世界と思考の内側が永久にかみ合わないでいたら——今は意図して思考の遊離をあそんでいるが、不随意に身体と心が離れつづけたら、身体と思考の重なりが断たれてしまったら、その時はおしまいなのだろうとも察した。おしまいというのは取り返しのつかなさだった。たとえばと妹は思う。今ここでこの海に飛び込んだらおしまいだ。もし溺れ死んだとしても、浮上して岸に戻ったとしても、寒くてずぶ濡れのみじめな身体で海岸を引き返さないといけない。どちらにせよ取り返しがつかないのだ。水死体に交わること、打ち上げられた魚やクラゲ、それらもまた妹が見たおしまいであることのひとつであった。妹はおしまいの瀬戸際で遊ぶことを覚えた。おしまいの寸前は魅力的だった。けれどもおしまいの向こう側を、妹は知らない。知りたくない。地続きの国境線を越えるよりもずっと、彼女の想像が及ばないほど、おしまいは隔てられている。
振り返るとヨドミ氏は足元に目を落としていた。緑がかった体色に赤い模様が入ったヒトデが堤防の上に落ちていた。妹はつま先で小突き、反応がないのを見て指でつまんでひっくり返した。ヒトデは乾いて固くなっていた。身体の裏側に生えた白い触手はすべて活動を止めていた。
ヨドミ氏にヒトデを差し出した。ヨドミ氏は受け取らなかった。妹はヒトデを海に捨てた。死体が海底に沈んでいくのを、ヨドミ氏は目で追った。
暮れなずむ空の端は薄桃色。
家の廊下に二人はいる。水を張った風呂桶に足を浸したヨドミ氏は、黙り込んで外の世界を眺めている。日差しは暖かくそよ風が冷たい。洗濯物は船の帆のように風をはらんでふくらんでいる。
妹はうずくまり、水死体の傍らにいる。触れそうなくらい近くにいたが、触れることはしなかった。触れたら戻れなくなると思った。
「ヨドミさん」
うずくまったまま声を掛けた。庭へ開け放たれた縁側の空気は肌寒かった。
あれから、妹は、集めたシーグラスをひっくり返し、本当の気に入りだけを残して、他を海にばらまいた。手元に残ったガラス片は白いのが一つと青いのが二つで、偶然による複雑なひび割れのために、光の加減で真珠層のような虹色が浮かび上がっていた。
彼女はガラス片を握りしめてまどろんでいる。
「ヨドミさん」
ガラスが擦れ合い甲高く鳴った。この鋭利な欠片で人肌を傷つけてしまいたい。
妹の腫れぼったい唇が半開きのまま言葉を探す。声を上げる前からすでに泣き出しそうだった。寝そべりながら身に降りかかる感傷とあそんでいた。結局、自分自身を除いて、遊び相手は現れなかった。
「ヨドミさん」
三たび声をかけた。
「どうして死んでしまったの」
けれど、死んでいなかったら、妹とその男は出会わなかった。
けれど、と妹は声を上げる。覚えたての感傷を振りかざして。感情がせめぎ合っているふりをしていた。道は、まったく一本道だったのに。
妹は彼の膝に頭をあずけて眠りたかった。それどころか、欲しかったのは、ただ一度の相槌だった。
『VANITAS』のその他の収録作品は、PDF版で配信しています。
『VANITAS』PDF版
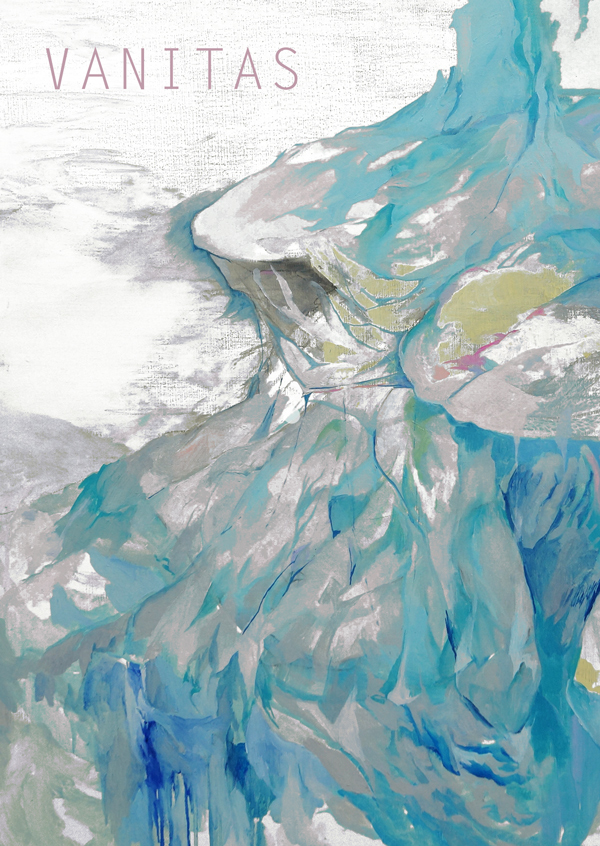
PDFダウンロード:
BOOTHでダウンロードする
当サイト内でダウンロードする
書籍概要
『VANITAS』スイマーズ発行、2014年初版
収録作:
『ワイン』 田中バイオ
『空の空』 佐藤芙有
『入江にて』山川夜高
『ガルシア』田中バイオ
価格:無料
category : novels / portfolio : personal works
